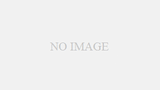犬にも夏バテがあるってご存知ですか。実は、猛暑で体調を崩してしまうワンちゃんも多いんです。
人と同じように、犬も食欲が落ちることがあるんですよね。そんなときにはフードでちょっとした工夫をしてみるといいかもしれません。
冷たいおやつや水分がたっぷりのフードなど、夏バテ対策にぴったりなアレンジがたくさんありますよ。
この記事では、犬の夏バテ対策としておすすめのフードアレンジをいくつかご紹介します。
参考にしていただければ嬉しいです。
犬が夏バテになる原因とは?フードの影響もある?

夏になると、なんだか愛犬がだるそうだったり、ご飯の食べが悪くなったりしていませんか?
実はそれ、「夏バテ」のサインかもしれません。
犬は人間よりも暑さに弱い生き物なので、ちょっとしたことで体に負担がかかってしまうんです。
そして、夏バテの原因には、環境だけでなく「食事=フード」が関係していることもあります。
ここでは、犬が夏バテになる主な原因を4つの視点から紹介していきます。
高温多湿の環境で体温調節がうまくいかないから
夏は気温だけでなく、湿度も高くなりますよね。
犬は人のように汗をかいて体温を調節することができないので、暑さが続くと体に熱がこもりやすくなります。
特に短頭種(パグやフレンチブルドッグなど)や毛が密な犬種は、熱がこもりやすいので注意が必要です。
お部屋が暑すぎたり、風通しが悪い場所で過ごしていると、それだけで夏バテの原因になってしまうことも。
扇風機や冷房をうまく使って、なるべく快適な環境をつくってあげたいですね。
冷房の効いた室内と外気温の差で自律神経が乱れるから
暑い外から帰ってきて、キンキンに冷えたお部屋に入ると、私たちでもちょっと体がだるくなりますよね。
犬も同じで、気温差が激しい環境を繰り返すことで、自律神経が乱れてしまうことがあります。
自律神経が乱れると、体の調節機能がうまく働かず、だるさや食欲低下などの夏バテ症状が出やすくなります。
冷房はもちろん必要ですが、温度設定を急激に下げすぎないようにしたり、外出後は徐々に体を慣らすなどの工夫が大切です。
冷えすぎた床で寝かせるのも体に負担をかけることがあるので、寝る場所にも気をつけてあげたいですね。
食欲が落ちることで栄養不足になりがちだから
暑さで食欲が落ちて、ご飯を残す日が増えると、自然と栄養不足になってしまいます。
栄養が足りないと体力も落ちて、さらに夏バテしやすいという悪循環に…。
特にビタミンB群やミネラル、タンパク質などは、夏の体調維持に欠かせない栄養素です。
「今日はちょっとしか食べなかったな…」という日が続くようであれば、食べやすいフードに切り替えてみるのも良いかもしれません。
見た目では元気そうに見えても、体の中ではバテていることもありますので、食事量のチェックはこまめにしておきたいですね。
消化に負担のかかるフードが体に負担をかけているから
夏バテのときって、私たちも脂っこいものや重たいものを避けたくなりますよね。
犬も同じで、脂肪分が多かったり、添加物が多いフードは、消化に時間がかかって体に負担をかけやすくなります。
胃腸が弱っているときにこういったフードを与えると、余計に調子が悪くなる原因になってしまうこともあります。
夏場はなるべく消化の良いフードを選んで、体にやさしい食事を心がけるのがおすすめです。
水分量が多いウェットタイプや、手作りスープごはんなども取り入れて、無理なく栄養を摂れるようにしてあげたいですね。
犬の夏バテの主な症状と見分け方【フードを食べないのはサイン?】

「いつもと様子が違うけど、これって夏バテなのかな?」
そんなふうに感じることってありませんか?
犬は自分で不調を訴えることができないからこそ、飼い主がちょっとした変化に気づいてあげることが大切です。
夏バテの症状には、わかりやすいものもあれば、一見すると気づきにくいサインもあるんですよ。
フードを食べる量が減ったり、食べなくなったりする
最も多く見られるのが「食欲の低下」です。
暑さで食欲が落ちるのは、犬にとってもよくある反応ですが、食べない日が続くのはちょっと注意が必要です。
いつも完食していた子が残すようになった、ごはんを前にしても見向きもしない…そんな変化があれば、夏バテの可能性も。
無理に食べさせるのではなく、フードの温度や香り、水分量などに工夫して様子を見るのがポイントです。
元気がなくなり、散歩を嫌がる
「いつもなら散歩に行くよって言うと飛びついてくるのに、今日は寝たまま…」
そんなときも、夏バテを疑ってみるといいかもしれません。
体がだるかったり、暑さで消耗していると、動きたがらなくなるのは自然な反応です。
無理に外に連れ出さず、お部屋で少し遊んでみたり、散歩時間を涼しい早朝や夜に変えてあげるだけでも犬の負担は軽くなります。
元気がない日は、まずは休ませてあげることが一番ですね。
下痢や嘔吐が見られる
夏バテによって胃腸が弱ると、消化不良を起こして下痢や嘔吐といった症状が出ることもあります。
とくにフードの変更や、水分不足、冷たいものの与えすぎなどが重なると、体に負担がかかってしまいます。
軽い症状なら1日様子を見てもいいですが、繰り返すようならすぐに獣医さんに相談を。
便の状態や頻度をメモしておくと、診察のときにとても役立ちますよ。
寝ている時間が極端に増える
夏はどうしても動きが鈍くなりがちですが、「あれ?今日ほとんど寝てばっかりだな」と感じたら、ちょっと気にかけてあげてください。
体力を温存しようとするために、眠って過ごす時間が増えるのも夏バテのサインのひとつです。
普段よりも反応が鈍くなったり、呼びかけても起きなかったりするときは要注意です。
食事・排せつ・睡眠、それぞれのバランスを見ながら、少しでも異変を感じたら体調チェックをしてみてくださいね。
犬の夏バテ対策におすすめのフードの選び方

夏バテ対策には、涼しい環境や適度な運動も大切ですが、やっぱり食事の工夫が一番効果的です。
どんなフードを選ぶかによって、愛犬の夏を快適に過ごせるかどうかが大きく変わってきます。
ここでは、夏バテを防ぐために意識してほしいフード選びのポイントをまとめました。
消化の良いフードを選ぶ
夏は胃腸も疲れやすくなるので、体にやさしいフードが基本です。
消化に時間がかかるフードは、体に負担がかかりやすく、夏バテの回復も遅れてしまいます。
原材料がシンプルで、穀物の量が少なめなフードや、良質なたんぱく質が中心のレシピが理想的です。
ふやかしやすいドライフードや、お腹にやさしい配合のものを選ぶことで、食べやすさもアップしますよ。
水分が多めのウェットフードを取り入れる
暑さで水を飲む量が減ってしまうワンちゃんも少なくありません。
そんなときは、水分を自然に摂れるウェットタイプのフードがおすすめです。
水を飲みたがらない子でも、フードから水分を補給できるので脱水の予防にもなります。
普段はドライフード中心の子でも、夏の間だけウェットフードを混ぜたり、切り替えるのもひとつの手です。
食いつきが良くなるというメリットもあるので、食欲が落ちているときに試してみてください。
ビタミンやミネラルがしっかり入った総合栄養食を選ぶ
栄養バランスが崩れやすい夏だからこそ、フードの中身にも気をつけたいところです。
特にビタミンB群やミネラル(ナトリウム、カリウムなど)は、体調を整えるのに欠かせません。
パッケージに「総合栄養食」と書かれているフードを選ぶと、必要な栄養素がしっかりとれます。
手作り食をしている方も、栄養が偏らないように意識して取り入れてみてくださいね。
低脂肪・高タンパクのバランスが取れたフードを選ぶ
暑い季節は、脂っこい食事は避けたくなるもの。それは犬も同じです。
夏は代謝が落ちやすいので、脂肪分の高いフードは胃腸に負担がかかりがちです。
一方で、タンパク質は筋肉や体力の維持に必要不可欠なので、しっかり摂らせたい栄養素です。
「低脂肪だけど高タンパク」というフードを選ぶことで、夏の体調をサポートしながら、無理なく続けやすいごはんになります。
気になるときは、獣医師さんに相談しながら選んでみると安心ですよ。
犬の夏バテを防ぐためのフードの与え方とタイミング

せっかく良いフードを選んでも、与える時間帯や方法によっては、食べてくれなかったり、体に負担がかかってしまうこともあります。
特に夏は、与え方を少し変えるだけで、食いつきや体調に大きな違いが出てくるんです。
食べるタイミングや量、温度などをちょっと工夫するだけで、夏バテ予防につながりますよ。
涼しい時間帯(朝や夜)に与える
真昼の暑い時間帯にご飯を出しても、犬も「今はいいや…」と食欲が湧かないことが多いです。
朝の涼しい時間や、夕方〜夜にかけて気温が落ち着いたころが、夏場の食事にちょうどいいタイミングです。
暑さで体力を消耗しているときに食べさせようとしても、うまく消化できないこともあるので注意が必要です。
クーラーの効いた部屋で落ち着いて食べられるよう、環境を整えてあげるのも大切ですね。
1日2回以上に分けて少量ずつ与える
夏は一度にたくさん食べるのがしんどく感じる子も多いです。
だからこそ、「1日1回ドカッと」よりも「少量ずつ複数回」に分けた方が、犬の体にはやさしいんです。
特に食欲が落ちているときは、無理に完食させようとせず、食べやすい量でこまめに与えてあげましょう。
おやつ代わりに少しずつ与える感覚で、「食べられたね、えらいね」と声をかけてあげるだけでも、食事の時間が楽しいものになりますよ。
常温に戻してから与える
冷蔵保存のウェットフードや手作りごはんをそのまま出していませんか?
冷たいご飯は、犬の胃腸に負担をかけやすく、夏バテの原因になってしまうことがあります。
電子レンジで温めすぎないよう注意しつつ、自然に常温に戻すのがおすすめです。
ぬるま湯で少しふやかすと香りも立って、食欲をそそる効果もありますよ。
食べない日が続く場合は、温度や硬さなども見直してみると、意外なところに原因が隠れていることもあります。
犬が夏バテでも食べやすいフードの工夫方法

夏バテで食欲が落ちているときでも、ちょっとした工夫を加えることで、愛犬がまたご飯に興味を持ってくれることがあります。
無理に食べさせるのではなく、「おいしそうだな」「食べてみたいな」と思える環境を作ってあげることが大切です。
香りや温度、食感などにひと工夫するだけで、食欲がぐっと戻ってくることもありますよ。
フードにぬるま湯をかけて香りを立たせる
ドライフードをそのまま与えても食べない…。そんなときは、ぬるま湯を少しかけてみてください。
お湯を加えることで、フードの香りがふわっと広がり、嗅覚が敏感な犬の食欲を刺激してくれます。
冷たいままだと香りが立ちにくく、食欲が湧きにくいこともあるので、常温~ぬるめの温度がポイントです。
ふやかすことで噛みやすくなり、消化も良くなるので、シニア犬や胃腸が弱っている子にもぴったりです。
鶏むね肉や野菜のトッピングで食欲を刺激する
フードだけだと食いつきが悪いときは、自然食材のトッピングを加えるのもおすすめです。
鶏むね肉・かぼちゃ・にんじんなどは、低脂肪で栄養価も高く、犬の胃腸にもやさしい素材です。
香りや見た目が変わることで、「今日はちょっと違うぞ?」と興味を持ってくれる子も多いです。
トッピングは少量で十分。あくまで“ごほうび”感覚で、主食のフードを引き立てる役割にしてあげましょう。
冷たいゼリータイプの犬用フードを取り入れる
暑い日には、冷たいものが欲しくなるのは犬も同じです。
最近では、水分たっぷりのゼリータイプの犬用フードも市販されていて、夏場にはとても重宝します。
食べやすくてひんやりしているので、食欲がないときの“リフレッシュおやつ”としても使えます。
ただし冷たすぎるものを一気に食べるとお腹に負担がかかるので、冷蔵庫から出して少し常温に戻してから与えるのが安心です。
食感や口当たりの変化で、マンネリ化したご飯に新鮮さをプラスしてあげましょう。
犬の夏バテ対策に役立つ手作りフードのポイント

「市販のフードを食べないけど、何かしてあげたい…」
そんなときに取り入れやすいのが、手作りのごはんです。
手作りといっても、難しいことをする必要はありません。食べやすくて、水分がしっかり摂れる工夫をするだけで十分なんです。
夏バテ中の犬でも無理なく食べられるような、体にやさしいレシピを意識してみましょう。
水分補給を意識したスープごはんにする
夏の暑さで水をあまり飲まなくなっている子には、スープごはんがとても効果的です。
食事の中で水分が摂れると、自然と脱水予防にもつながります。
鶏肉や野菜を煮込んだスープをベースに、ご飯やフードを少し混ぜてあげるだけで、栄養も水分も補給できます。
香りも豊かになるので、食欲が落ちているときでも「ちょっと食べてみようかな」と思えるごはんになりますよ。
ささみ、かぼちゃ、きゅうりなどの食材を使う
夏バテ対策におすすめの食材は、消化がよくて栄養価が高いもの。
たとえば、脂肪が少なくて高たんぱくな「ささみ」、βカロテン豊富な「かぼちゃ」、水分が多い「きゅうり」などは、夏にぴったりです。
シンプルな茹で調理でOK。味付けは一切しないで素材のうまみをそのまま活かすのが基本です。
アレルギーがないか、過去に食べて大丈夫だったかを確認しながら、少量ずつ取り入れてみてくださいね。
冷やしすぎず常温で与える
「暑いし、冷たいごはんのほうがいいかな?」と感じることもあると思います。
でも、冷たすぎるものはお腹に刺激が強く、逆に体調を崩してしまう原因になってしまうことも。
冷蔵保存していた手作り食は、必ず常温に戻してから与えるようにしましょう。
電子レンジで温めすぎると熱くなりすぎるので、自然解凍やぬるま湯で調整するのが安心です。
ほんの少しの温度の違いでも、食べるかどうかが変わることもあるので、様子を見ながら調整してみてくださいね。
犬の夏バテにフード以外でできるサポート方法

夏バテ対策というと「食事」が注目されがちですが、それ以外にもできることはたくさんあります。
日常の過ごし方や、ちょっとした環境づくりの工夫でも、愛犬の体調はグッと安定してくるんです。
ごはんだけじゃなく、生活全体を見直してあげることが、夏を元気に乗り越えるカギになりますよ。
室温を25℃前後に保ち、涼しい環境を整える
人がちょっと暑いと感じるくらいの気温でも、犬にとってはかなりしんどいことがあります。
特に毛が多い犬種や短頭種の子たちは、熱がこもりやすく、体温調節が苦手なんです。
室温は25℃前後をキープするのが理想。冷房や扇風機を上手に使いながら、快適な空間をつくってあげましょう。
直射日光が当たらない場所にベッドを置くのもおすすめです。
こまめな水分補給を促す
夏バテを防ぐために欠かせないのが、水分補給です。
ただし、暑いからといって自分からたくさん水を飲むとは限らないのが犬の難しいところ。
水飲み場を複数置いたり、お気に入りの器に変えてみると、飲む量が増えることもあります。
フードやおやつに水分を加えてあげるのも、自然な水分補給の一つですよ。
散歩は早朝や夜にする
真昼のアスファルト、実は想像以上に熱くなっていて、犬の足裏にはとても危険です。
地面の熱で肉球をやけどしてしまったり、熱中症のリスクもぐっと高まります。
できるだけ日が昇る前の早朝や、日が落ちた夜にお散歩へ行くのがベストです。
もし日中しか時間が取れないときは、日陰を選んだり、短時間にするなど工夫してあげてくださいね。
クールマットやひんやりグッズを活用する
夏に人気のクールマットや冷感ベッド、冷やして使うおもちゃなども、夏バテ対策にとても役立ちます。
犬自身が「涼しい場所」を選んでくつろげるようにしてあげることが大切です。
保冷剤をタオルで包んでケージに置くなど、手軽にできる工夫もたくさんあります。
もちろん、冷やしすぎには注意しながら、心地よく過ごせる“ひんやり空間”を用意してあげましょう。
まとめ:犬の夏バテ対策はフードの工夫で効果的に

夏の暑さは、犬にとっても本当にしんどいもの。いつも通りに過ごしているように見えても、実は体に負担がかかっていることもあります。
だからこそ、毎日のごはんを見直してあげるだけでも、夏バテ対策としてとても効果的なんです。
ちょっとした工夫で、食欲が戻ったり、元気に過ごせたりするようになると、私たちもホッとしますよね。
体調や食欲に合わせてフードを見直すことが大切
食べる量が減った、食いつきが悪い…そんなときは、フードが体に合っていないのかもしれません。
無理に今のまま続けず、消化に良いものや水分の多いものに変えてあげるのもひとつのやさしさです。
愛犬の体調や食欲に寄り添って、ごはんの内容や与え方を柔軟に変えていくことが、夏バテ予防の第一歩です。
手作りや水分補給の工夫で夏を快適に過ごさせる
食べやすさを重視した手作りごはんや、ウェットフード、スープごはんなどは、夏にはとても頼もしい存在です。
「おいしそう」と思ってくれるような香りや見た目、水分量のバランスも大切にしてあげたいですね。
無理に食べさせるのではなく、「自然と食べたくなる」環境をつくってあげるのが理想的です。
症状が続く場合は早めに獣医師に相談する
いくら工夫しても食べない、下痢や嘔吐が続いている、元気がない…そんなときは、自己判断せずに獣医さんに相談しましょう。
夏バテだと思っていたら、実は別の病気が隠れていたというケースもあります。
「ちょっと気になるな」という段階で診てもらうことで、早めに対処できて安心です。
何より大切なのは、愛犬の変化にいち早く気づいてあげること。夏の間も、元気に過ごせますように。